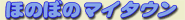もう一度読みたい【エッセイ・自分たち探し】
フリージャーナリスト 國米 家己三さんのシリーズエッセイ
文化の成熟した社会が"川柳ブーム"を生んでいます
いま、世は"川柳ブーム"といっていいようです。
企業が、自社のPR企画として川柳を公募するケースがあり、これに便乗したのか奈良県や姫路市などが、やはり賞金付きで一般市民から句を募っています。NHK大阪の「ぼやき川柳」も、その路線といえるでしょう。
俳句が、自然を季題入りで詠むのに対して、川柳は人情の機微というか世態の裏面をつくというか、あくまで真っ当に、大真面目に生きている人間たちの姿を、視点を変えて珍奇でおかしく、けったいなものに浮き彫りにする。そこに川柳の妙味があるのでしょう。文化的に成熟した社会では、川柳読みが盛んになるのは至極もっともなことではないでしょうか。ちなみに、川柳の始まりは江戸時代後期です。
ただ、毎年話題になる第一生命保険が募集する「サラリーマン川柳」は今年26回目。14年ぶりに3万句を越える応募があったそうですが、句の質は少々マンネリ化の感じ。これはというシャープな句が少なかったような気がします。「携帯と亭主の操作は指一本」「党名を覚える前に投票日」あたりが目立ちましたが、川柳の出来としてはイマイチ。新聞各紙の扱いも今年は哀れなほど小さいものでした。昭和62年第1回の「サラ川」では「一戸建て手が出る土地は熊も出る」なんてのが発表され、当時としては極めて意表をつく句として高く評価されたものです。その後も「このオレにあたたかいのは便座だけ」「まだ寝てる帰ってみればもう寝てる」「やめるのか息子よその職俺にくれ」「犬はいい崖っぷちでも助けられ」などの秀作がつづきました。
しかし、ここ数年は潤いを欠く乾いたような句が多くなっているといわれてます。昨年の応募作ですが「仕事やれ人に言わずにお前やれ」「宝くじ『当たれば辞める』が合言葉」などはその典型でしょう。
最近、シルバー川柳というのが、ひとつの領域を拓いています。定年後、暇に十分恵まれた高齢者が取り組むにはかっこうの対象。「失敗は創作料理と言って出し」などいいできですね。「あすは散るでも今日は生きてる桜」も年輪を重ねた人だからこその作です。「遺影用笑い過ぎだと却下され」「若づくり席をゆずられムダを知り」「お辞儀して共によろけるクラス会」…。こうなると若い世代の「サラ川」を完全に句っている、いや食っているじゃありませんか。みごとです。
ただし、「万歩計半分以上は探しもの」「紙とペン探してる間に句を忘れ」「立ち上がり用事を忘れてまた座る」「探し物やっと探して置き忘れ」「忘れ物口で唱えて取りに行き」とボケ初期を材料にした句が圧倒的に多いのも「シル川」の特徴。こちらはパターン化が心配です。今後は、物忘れにひとひねり、ふたひねり加えないと、見むきもされなくなるでしょう。
一方子どもたちの句作も注目に値します。小中学生はまだ、人の暮らしをうがってみたり世間を風刺するまでに成長しているわけではないので川柳詠みは、まだ無理です。しかし、足立区の炎天寺が全国の小中学生からあつめる俳句は毎年12万前後に達しますが、それをみるとなかなかに結構、川柳的なものがある。子どもたちは、俳句と川柳の区別など超越し自由にとらえているため、結果として川柳風になってしまうのでしょう。
たとえば「かまきりのちょうなんじなんみつけたよ」(石川、小学1年)「夏休み足のゆびまでねむくなり」(東京、中学1年)「田植えして歌舞伎役者の顔になる」(愛媛、中学2年)「花ふぶきやむまで車列渋滞す」(福島、小学5年)「あつい夏宿題たちものぼせてる」(群馬、小学2年)などがそれ。
川柳詠みの予備軍が無数に育っているのです。伝統の強みがこの世界にもちゃんと生きている、ということで、頼もしい限りです。
いま、世は"川柳ブーム"といっていいようです。
企業が、自社のPR企画として川柳を公募するケースがあり、これに便乗したのか奈良県や姫路市などが、やはり賞金付きで一般市民から句を募っています。NHK大阪の「ぼやき川柳」も、その路線といえるでしょう。
俳句が、自然を季題入りで詠むのに対して、川柳は人情の機微というか世態の裏面をつくというか、あくまで真っ当に、大真面目に生きている人間たちの姿を、視点を変えて珍奇でおかしく、けったいなものに浮き彫りにする。そこに川柳の妙味があるのでしょう。文化的に成熟した社会では、川柳読みが盛んになるのは至極もっともなことではないでしょうか。ちなみに、川柳の始まりは江戸時代後期です。
ただ、毎年話題になる第一生命保険が募集する「サラリーマン川柳」は今年26回目。14年ぶりに3万句を越える応募があったそうですが、句の質は少々マンネリ化の感じ。これはというシャープな句が少なかったような気がします。「携帯と亭主の操作は指一本」「党名を覚える前に投票日」あたりが目立ちましたが、川柳の出来としてはイマイチ。新聞各紙の扱いも今年は哀れなほど小さいものでした。昭和62年第1回の「サラ川」では「一戸建て手が出る土地は熊も出る」なんてのが発表され、当時としては極めて意表をつく句として高く評価されたものです。その後も「このオレにあたたかいのは便座だけ」「まだ寝てる帰ってみればもう寝てる」「やめるのか息子よその職俺にくれ」「犬はいい崖っぷちでも助けられ」などの秀作がつづきました。
しかし、ここ数年は潤いを欠く乾いたような句が多くなっているといわれてます。昨年の応募作ですが「仕事やれ人に言わずにお前やれ」「宝くじ『当たれば辞める』が合言葉」などはその典型でしょう。
最近、シルバー川柳というのが、ひとつの領域を拓いています。定年後、暇に十分恵まれた高齢者が取り組むにはかっこうの対象。「失敗は創作料理と言って出し」などいいできですね。「あすは散るでも今日は生きてる桜」も年輪を重ねた人だからこその作です。「遺影用笑い過ぎだと却下され」「若づくり席をゆずられムダを知り」「お辞儀して共によろけるクラス会」…。こうなると若い世代の「サラ川」を完全に句っている、いや食っているじゃありませんか。みごとです。
ただし、「万歩計半分以上は探しもの」「紙とペン探してる間に句を忘れ」「立ち上がり用事を忘れてまた座る」「探し物やっと探して置き忘れ」「忘れ物口で唱えて取りに行き」とボケ初期を材料にした句が圧倒的に多いのも「シル川」の特徴。こちらはパターン化が心配です。今後は、物忘れにひとひねり、ふたひねり加えないと、見むきもされなくなるでしょう。
一方子どもたちの句作も注目に値します。小中学生はまだ、人の暮らしをうがってみたり世間を風刺するまでに成長しているわけではないので川柳詠みは、まだ無理です。しかし、足立区の炎天寺が全国の小中学生からあつめる俳句は毎年12万前後に達しますが、それをみるとなかなかに結構、川柳的なものがある。子どもたちは、俳句と川柳の区別など超越し自由にとらえているため、結果として川柳風になってしまうのでしょう。
たとえば「かまきりのちょうなんじなんみつけたよ」(石川、小学1年)「夏休み足のゆびまでねむくなり」(東京、中学1年)「田植えして歌舞伎役者の顔になる」(愛媛、中学2年)「花ふぶきやむまで車列渋滞す」(福島、小学5年)「あつい夏宿題たちものぼせてる」(群馬、小学2年)などがそれ。
川柳詠みの予備軍が無数に育っているのです。伝統の強みがこの世界にもちゃんと生きている、ということで、頼もしい限りです。