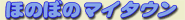もう一度読みたい【エッセイ・自分たち探し】
フリージャーナリスト 國米 家己三さんのシリーズエッセイ
「アーティスト症候群」と「芸芸シンドローム」
数ヶ月前のことですが、某紙に「紳士淑女教育家」 という珍妙な肩書をもった女性が登場しました。
世界の王室など国際交流の場での正式なマナーを日本人に教えるのが仕事だとか。
それにしてもこの肩書、 新聞社の編集部がつけたというより、 本人からの申し出によるものでしょうが、 あまりにもセンスがずっこけているというか、大時代な感じ。 ただただ恐れ入るしかありません。
これに比べれば、近ごろ増えた「アーティスト」 の肩書をもつ名刺を持ち歩く人たちなど、まだかわいい部類。
もっとも、ただ「アーティスト」だけでは画家なのか、 彫刻家なのか、音楽家なのか、はたまた映画やってるのか、演劇やってるのか、わからない。
わからないところがミソ、「わたし、なんでもアートしちゃうもん!」なのかも知れません。
その反面、専門分化してマニキュアの 「ネイル・アーティスト 」、美容の「 ヘア・アーティスト 」、 生け花の「 フローラル・アーティスト 」といったぐあいに、このかっこいい 「 アーティスト」がいろんな形で使われているのです。
そこで早速、現れました、「アーティスト症候群 」なる新刊本。
そこには 「アーティスト、アーティストと石を投げたら必ずアーティストに当たるぐらいの人口密度で、 芸能人など副業でアーティストになりたがる人も少なくない。 俗世間から一線を画して一生を芸術に捧げようという孤独な覚悟もなければ、一種、病のような創作意欲もない。 人からアーティストと呼ばれたいという『被承認欲 』だけでそれを名乗っている」(要旨)
と書かれています。
軽佻浮薄、おいしそうな新しい世の流れができると、 すぐそれに便乗する人たちだと痛烈に批判しているのです。
著者の大野佐紀子さんは、 天下の東京芸術大学は彫刻科卒。
20年ほど実際の創作現場で活躍、現在は名古屋芸術大学やデザイン専門学校非常勤講師。
ただ、金銭の保証もないなか、命をけずり血を吐く思いでオーソドックスに正真正銘の芸術家が挑戦 しているファインアートの世界がある一方で、 ファッションや工業デザイン、アニメ、 マンガその他、 感性で勝負するジャンルが近年一層大きく広がってきたことが「アーティスト」 の肩書乱用の背景にあることも見逃せません。
しかも、 この国では昔から広い分野で芸術志向がつよかったのです。
芸術には距離があるけれど、芸術に近づきたいという衝動が、多くの領域にありました。
そのいい例が「工芸」「農芸」「園芸」「陶芸」「漆芸(しつげい)」「武芸」のように、 「芸」が至るところで用いられています。
「技芸」「民芸」 「演芸」 「話芸」、そして「手芸」に「足芸」。 さらには「曲芸」 「水芸」 「大道芸」「職人芸」 「名人芸」…。
まさに「芸芸シンドローム」 といったところですが、 この辺になると芸術というより技(わざ) のニュアンスが濃くなっています。
それでも芸術的でありたい、 芸術もどきでもいい、 そこに少しでもかかわっていたいという 意識が深層に存在しているのがわかります。
余談ですが、 こんなにあって、なぜ、ないのかと思うのが「畜芸」。
日本の霜降り肉は、 いまや世界的なブランド。
これを口にしたアメリカの有名なスポーツ選手があまりのおいしさに感動、 わざわざ神戸まで飛んできて「 自分の息子の名はワギュウ(和牛)にした 」 と語ったというエピソードもあるほど。
以前からのこうした芸術志向の水脈が、現代の日本社会にも生きているからこそ、 「アーティスト」を名乗る人々が多いと考えられるわけで、「アーティスト」 氾濫は、 まあ、 許容範囲のうちというしかないのではないでしょうか。
世界の王室など国際交流の場での正式なマナーを日本人に教えるのが仕事だとか。
それにしてもこの肩書、 新聞社の編集部がつけたというより、 本人からの申し出によるものでしょうが、 あまりにもセンスがずっこけているというか、大時代な感じ。 ただただ恐れ入るしかありません。
これに比べれば、近ごろ増えた「アーティスト」 の肩書をもつ名刺を持ち歩く人たちなど、まだかわいい部類。
もっとも、ただ「アーティスト」だけでは画家なのか、 彫刻家なのか、音楽家なのか、はたまた映画やってるのか、演劇やってるのか、わからない。
わからないところがミソ、「わたし、なんでもアートしちゃうもん!」なのかも知れません。
その反面、専門分化してマニキュアの 「ネイル・アーティスト 」、美容の「 ヘア・アーティスト 」、 生け花の「 フローラル・アーティスト 」といったぐあいに、このかっこいい 「 アーティスト」がいろんな形で使われているのです。
そこで早速、現れました、「アーティスト症候群 」なる新刊本。
そこには 「アーティスト、アーティストと石を投げたら必ずアーティストに当たるぐらいの人口密度で、 芸能人など副業でアーティストになりたがる人も少なくない。 俗世間から一線を画して一生を芸術に捧げようという孤独な覚悟もなければ、一種、病のような創作意欲もない。 人からアーティストと呼ばれたいという『被承認欲 』だけでそれを名乗っている」(要旨)
と書かれています。
軽佻浮薄、おいしそうな新しい世の流れができると、 すぐそれに便乗する人たちだと痛烈に批判しているのです。
著者の大野佐紀子さんは、 天下の東京芸術大学は彫刻科卒。
20年ほど実際の創作現場で活躍、現在は名古屋芸術大学やデザイン専門学校非常勤講師。
ただ、金銭の保証もないなか、命をけずり血を吐く思いでオーソドックスに正真正銘の芸術家が挑戦 しているファインアートの世界がある一方で、 ファッションや工業デザイン、アニメ、 マンガその他、 感性で勝負するジャンルが近年一層大きく広がってきたことが「アーティスト」 の肩書乱用の背景にあることも見逃せません。
しかも、 この国では昔から広い分野で芸術志向がつよかったのです。
芸術には距離があるけれど、芸術に近づきたいという衝動が、多くの領域にありました。
そのいい例が「工芸」「農芸」「園芸」「陶芸」「漆芸(しつげい)」「武芸」のように、 「芸」が至るところで用いられています。
「技芸」「民芸」 「演芸」 「話芸」、そして「手芸」に「足芸」。 さらには「曲芸」 「水芸」 「大道芸」「職人芸」 「名人芸」…。
まさに「芸芸シンドローム」 といったところですが、 この辺になると芸術というより技(わざ) のニュアンスが濃くなっています。
それでも芸術的でありたい、 芸術もどきでもいい、 そこに少しでもかかわっていたいという 意識が深層に存在しているのがわかります。
余談ですが、 こんなにあって、なぜ、ないのかと思うのが「畜芸」。
日本の霜降り肉は、 いまや世界的なブランド。
これを口にしたアメリカの有名なスポーツ選手があまりのおいしさに感動、 わざわざ神戸まで飛んできて「 自分の息子の名はワギュウ(和牛)にした 」 と語ったというエピソードもあるほど。
以前からのこうした芸術志向の水脈が、現代の日本社会にも生きているからこそ、 「アーティスト」を名乗る人々が多いと考えられるわけで、「アーティスト」 氾濫は、 まあ、 許容範囲のうちというしかないのではないでしょうか。